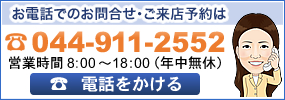解体≠墓じまい。「見た目のマジック」とお墓の再出発
2025年11月20日(木)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
昨日、「墓じまいの数字の見え方」について書きました。
墓じまいが10年で2倍になった、不要墓石が2万5000基ある……。
そうしたインパクトの強いニュースに、
現場として少し違和感があるという内容でした。
今回は、その続きとして。
『壊しても墓じまいとは限らない』 という
もう一つの現場のリアルを書いてみたいと思います。
壊す≠墓じまい
ある寺院墓地にある、お墓の相談を受けたときのことです。
代が変わり、直系の継承者はいなくなる。

解体前の墓所。大谷石製の外柵、コンクリート製の石塔中台
しかし、甥御さんが「家の墓として自分がついでいく」と
手を挙げてくださいました。
傍系であっても、お墓はきちんとつないでいくことができます。
ただ、現場を確認すると課題がいくつか見えてきました。
外柵は大谷石製で、長年の風雨にさらされ角は丸くなり、
だいぶ傷んできていました。
さらに納骨室は現場打ちのコンクリート製で、
収蔵可能な骨壺の数はわずか4つでした。
前回納骨時に、お骨をおさめて計4つ収蔵。
今回ご不幸があって、5つ目のお骨を納めなくてはなりませんでした。
それだけでも限界ですが、致命的だったのは
納骨室に水抜き穴がないことでした。

解体した旧墓地の納骨室。現場打ちのコンクリート製で、水抜き穴がありませんでした
上から降った雨がそのまま納骨室内にたまり、
前回の時も、大切なご先祖のお骨が完全に
水没してしまっていたのです。
これは石材店の施工とは考えにくく、
お墓の構造を充分に理解していない業者が
建てたものでしょう。
この状態のまま甥御さんに継いでもらうことは、とてもできません。
つまり今回は、
『お墓を壊すところから、つなぐ作業が始まる』
そうした現場だったのです。
残すために「壊す」。受け継ぐための決断
ご家族と話し合った結果、選択肢は二つありました。
-
元の場所に外柵を新しく作って再建する
-
同じ寺院内の別の墓域へ移す
今回は後者の「移す」という選択に。
偶然、同じ寺院内に、外柵は完成しているものの、
まだ使用者が決まっていない区画がありました。
そこへ石塔を移すことで、同じお寺で変わらずに
ご先祖を供養していくことができます。
ご親族間でいろいろな条件を考慮され、
納得されたうえでの判断でした。
したがって、元の区画は、外柵も石塔の中台(コンクリート製)も、
すべて解体します。
解体が終わり、更地になった様子だけを見ると、
誰の目にも“墓じまい”ですよね。

解体工事が完了した旧墓所
石塔がなくなり、外柵がなくなり、更地が残る。
そこだけ切り取れば、「あぁ、墓じまいなんだな」と思われても
仕方ない光景です。
しかし実際にはまったく逆で、
お墓は終わるどころか「これからまた始まる」 のです。
新しく作り直すことで、次の世代へつながる
移した先の新しい墓所では、
旧墓地の弱点を一つ一つ解消しながら再構築を行いました。
-
中台・芝台(石塔の下のほうの部材)を御影石で新調
- 水鉢も切出しの一体型に変更
-
香炉も新調

新調した芝台(しばだい)。納骨室の屋根と石塔の土台を兼ねる石です
旧墓地では中台がコンクリート製で、再利用には向きません。
加えて納骨室の屋根になるべき芝台がない。
それを今回はすべて御影石に作り替え、据え付けます。
耐久性・安定性ともに何十年も耐えていけるお墓になります。

古い墓所から移設。御影石の中台・芝台・切出水鉢・香炉を新調し、立派なお墓になりました。
大きな災害がなければ、
甥御さん、そして次の世代へと、しっかりつながっていきます。
その土台がようやく整ったと言えるでしょう。
現象ではわからない、目に見えない想い
今回の現場のように、
-
墓地の継承者はいる
-
供養は続く
-
石塔も残し、むしろ以前より良い形で再建される
あるいは、生活圏の近くにお墓を引っ越す。
こうした事例は決して少なくありません。
にもかかわらず、
旧墓地は更地になるため、
外から見れば墓じまいにしか見えない。
これが、前回の記事で書いた
『数字のマジック』に加えて『見た目のマジック』です。
数字は実態を映さないことがある。
そして、目に入る風景もまた、必ずしも実態を映しているとは限らない。
現場には、
壊しても終わらない、壊すことでつながるお墓
が確かに存在します。
お墓は壊して終わる場所ではなく、家族の物語を紡ぐ場所
墓じまいを否定したいわけではありません。
必要な墓じまいもありますし、
どうしても継ぐ人がいないケースもあります。
しかし、
「壊している」=「終わらせている」と
一足飛びに結びつけてしまうのではなく、
その背景にある事情や、残そうとしている想いにも
目を向けてみたいところです。
お墓は、本来 『つなぐための場所』 です。
状況によっては壊すところから始まることもありますし、
場所を移すことでつながることもあります。
寺院墓地や霊園で、隣や近くの区画が更地になっている。
そんな光景を目にする機会が増えているかもしれません。
「やっぱり墓じまいが増えているんだ」
「うちもそろそろ決断しないと……」
そう感じて、焦ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
でも、その更地が本当に「墓じまい」なのか、
それとも今回のような「移転」や「建て替え」なのかは、
外から見ただけでは分かりません。
大切なのは、周りの状況に流されず、
ご自身のお墓について、ご家族とじっくり話し合うこと。
継ぐ人がいるのか。お墓の状態はどうなのか。
これからどうしていきたいのか。
その答えは、ご家族ごとに違うはずです。
「壊す=終わり」と決めつけず、選択肢を知ったうえで、
納得のいく決断をしていただきたい。
私は、そう願っています。
では。
▼前回の記事:
墓じまい、その「数字のマジック」と現場のリアル
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
 現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム