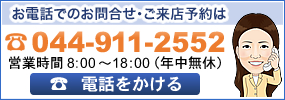大らかさって?〜刺身の「つま」と妻、そしてお墓の文字のお話
2025年11月9日(日)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
言葉には、それが使われてきた時間や背景があります。
そして文字にもまた、時代ごとの選ばれ方があります。
今回は、「つま」という言葉の由来から始まり、お墓に刻まれた文字に残る
「大らかさ」について少し考えてみたいと思います。
「つま」の由来と音の広がり
今朝、SNS上で見かけた対談動画の中で、「妻という言葉は、刺身のツマと同じで良くない」
という趣旨の話が出ていました。
言われてみれば同じ音ですし、配偶者を「添え物」のように扱う表現だと
感じる人がいても不思議ではありません。

ただ、言葉というものは案外おおらかです。
「つま」の語源については諸説あり、一説にはどちらも古い「端(つま)」という
言葉から派生したとされているようです。
「端」は「はし」「そば」を意味し、そこから「そばにいる人=妻」、
「そばに添えるもの=つま」と、方向の違う意味が生まれたと考えるわけです。
一方で、もともと別々の言葉だったものが、同じ音を持っていたために
後の時代で重なっていった、という見方もあります。
実際、江戸時代の料理書には、刺身の添え物を「妻」と書いた例が残っているということ。
「主のそばに寄り添うもの」という感覚が重なったのだと思います。
つまり、言葉は「音」が先にあり、その音に「字」が添えられていく。
そこに良し悪しを持ち込むと、本来の成り立ちが見えなくなってしまう。
言葉は、使われ続ける中で形を変え、意味を育てていくものだからです。
お墓の文字にも見える「大らかさ」
この感覚は、お墓に刻まれた文字にもそのまま見て取れます。
たとえば、私の名字「吉澤」もそうです。「吉」という字は、
上の部分が「士」の形で刻まれることもあれば、
「土」に近い形で刻まれているお墓もあります。
これは誤りではなく、「吉」には筆写や石刻の中で複数の字形が
併存していたためです。
実際、「吉田」さんなどでも「上が土型」の字を代々受け継いでいる家は
珍しくありません。
文字は、土地と時代の中で自然に息づいてきたものです。
「澤」と「沢」も同じです。うちの明治期のお墓では「沢」と刻まれていますが、
これも略字体が生活の中で普通に使われていた流れの中にあります。
「正しい字」が時代に応じて揺れるのは、ごく自然なことです。
異体字という文化の懐の深さ
「斎藤」さんの「斎」もわかりやすい例でしょう。
- 齋
- 齊
- 斉
齋 / 斎 / 齊 / 斉
これらはもともと同じ意味を持つ異体字で、時代や地域、行政実務の都合など
に応じて複数の形が並行して生きてきました。
「異体字」というのは、音も意味も同じでありながら、形だけが違う文字のことです。
日本の文字文化では、こうした異体字が自然に共存してきました。
どれが「正しい」ということではなく、それぞれの字形に歴史があり、
使われてきた理由がある。
お墓の文字を見ていると、その豊かさを実感します。
古いお墓には、それぞれの字が静かに、しかし、しっかりと残っています。
名前に込められた「願い」
また、「太郎」が「太良」と刻まれている例もあります。
これは単なる縁起担ぎではなく、「良」を名乗り字として用いる習慣が広く存在していた
時期があったためです。
実際、うちの先祖も「藤三郎」と記されている時もあれば「藤三良」とされている時も
あります。同一人物か、同じ名乗りを継いだ別の人物かは定かではありませんが、
時代の中で表記に揺れが生じていたことがわかります。
いずれにせよ、同じ名前であっても、用いられる文字は一定ではありませんでした。
時代の習慣や書き手の感覚によって、自然に揺れが生まれていたのだと思います。
つまり、「郎」も「良」も「ろう」と読まれ、どちらも自然な名前の形でした。
そこには、その字に託した人々の願いが込められているのです。
「正しさ」ではなく「その時代のままに」
こうして見てみると、昔の人は文字を「間違いか正しいか」で判断してはいませんでした。
音が同じなら通じる。
そのうえで「どの字を選ぶか」に、祈りや願いや美意識が宿る。
文字は、形そのものが「その家の歴史」なのだと思います。
だから古いお墓の文字を見るとき、「違う」と切り捨てるのではなく、
「その時代には、そのように書かれていたのだ」と受け取ることが大切だと
私は感じています。
文化は、静かに受け継がれていく
刺身のつまと、お墓の文字。一見、無関係にみえる話ですが、
どちらも言葉と字が「生き続けるもの」であることを教えてくれます。
言葉も文字も、誰かが使い続けたからこそ、今に残ってきました。
文化とは、声高に主張して守るものではなく、ただ人々に受け継がれていくことで
生きていくものなのだと思います。
お墓に刻まれた一字一字には、その家が歩んできた歴史が宿っているのです。
そんなことを、皆さんには知っていただけると嬉しいです。
では。
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
 現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム