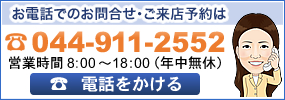とあるシンポジウムで感じたこと——お墓のありかたについて
2025年9月27日(土)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
昨年の今頃だったでしょうか。とあるシンポジウムに参加したときのことを、ふと思い出しました。テーマは樹木葬を中心とした新しい供養の形について。石屋という仕事をしていると、どうしても現場のことばかりに目が向きがちですが、外の世界に触れることの大切さを感じた一日でした。
里山再生型樹木葬という取り組み
特に心に残ったのは、一関市のあるお寺さんで行われている里山再生型樹木葬の取り組みです。単に木の根元に遺骨を納めるのではなく、その土地にあった里山の植生を徹底的に再現して、自然環境の再生とともに人が眠る。まるで森そのものが供養の場になっているようで、都会で見かける、整えられた公園のような“いわゆる樹木葬”とは一線を画すものでした。

AI生成によるイメージ画像(当該寺院とは関係ありません)
正直、石屋でなければ、こういうところに眠りたいと思うほど感銘を受けました。
シンポジウムで感じたこと
また、“いわゆる樹木葬”に対する彼らの問題意識については、確かにそうだなと思うところもありました。
しかし、その場で語られていた内容には、ほんの少し引っかかるものも、実はありました。樹木葬という「新しい供養の形」を語ること自体が、どこか従来のお墓のあり方を「時代に合わない」として位置づけているように感じられたからです。
「私たちが始めた」「理念が正しく伝わらない」といった表現が繰り返される中で、聞いているうちに、多様化を語りながらも、結果的には特定の方向に導かれていくような雰囲気を感じました。新しい取り組みこそが「正しい方向」であるかのように聞こえる場面もあり、違和感を覚えたのです。
もしこの論調が強く続くようなら、「多様性という名の排他性」につながりかねない——そんな懸念が頭をよぎりました。多様性とは本来、異なる価値観が並立することであり、ある価値観だけを「正しい」と押し出すことではないはずです。
あらためて振り返ると、「私たちが文化を変えた」と強調されていた言葉も、実際には“供養の選択肢を増やした”ということなのではないかと思います。たとえばフォーラムで語られていた「お一人様の女性が入るお墓がなかった」という話も、既存のお墓に代わる場(形)を用意したという意味では大切な取り組みです。けれども、それが従来のお墓や供養方法を全て否定する理由にはならないはずです。
私はこの点だけはしっかり言葉にしておきたいと思います。
そして貴重な気づきを与えてくださったシンポジウムの関係者の皆様には、心から感謝をしています。
文化と流行の違いを考える
時間が経った今、あらためて考えるのは「文化はもっと長い時間で育つものだ」ということです。
人の一生よりずっと短い時間で、「文化として定着した」と評価するには、まだ早いのかもしれません。
お墓や供養の形は、何十年、何百年もかけて人々に選ばれ、少しずつ変遷をたどりながら定着していくものです。そうした観点に立てば、今はまだ試行錯誤の段階にある——そう考える方が自然だと思います。
思えば10数年前、「終活」という言葉が出始めて以降、メディアでも頻繁に取り上げられ、関連書籍も次々と出版されていました。当時のエンディング産業展では、ステージイベントや講演も華やかで、会場全体が熱気に包まれていたのを覚えています。それが今では随分と控えめな雰囲気になり、来場者も落ち着いてきています。流行とはそういうものです。
注目を集め、やがて落ち着き、淘汰され、残るものだけが残る。新しい供養の形についても、これから数十年の間にふるいにかけられ、本当に必要とされるものだけが残っていくのでしょう。
日本の文化を日本の視点で
以前から、報道や終活業界での話題で少し気になっているのは、「諸外国ではこうだから」という比較が繰り返し語られることです。もちろん参考になる点も多いのですが、日本におけるお墓のあり方を考えるときには、まず第一に日本人のお墓、日本のお墓という視点を忘れてはならないと思います。
近年の議論を見ていると、この視点が少し置き去りにされがちな印象を受けます。もしこの視点が失われてしまえば、どこに軸足を置いて考えるべきかがあいまいになり、日本のお墓文化そのものが揺らいでしまうのではないか——そんな危惧さえ覚えます。
本質を見失わないために
形が変わるのは自然なことですが、本質は変わってはいけないと考えています。生活者のニーズに合わせてお墓の形が変化していくのは時代の流れですし、私自身それに反対するつもりはありません。
しかし最近では、話題性やデザインを前面に押し出した合葬墓が次々と登場しています。ピラミッド型や古墳型など、形状に強いインパクトを持たせたものも見かけます。もちろん新しいデザインを一概に否定するつもりはありませんが、仏教を中心に育まれてきた日本の供養のあり方に、古墳時代の墳墓の形や異国の墓制の意匠をそのまま持ち込むことには、どうしても慎重にならざるを得ません。
確かに今では天皇陵とされる古墳に鳥居が立っていますが、当時の葬送儀礼は今の神道とは異なるものでした。日本の歴史は、神道と仏教が共存し、時に融合してきた長い過程の上にあります。その流れを踏まえずに「形」だけを借りてしまうことには、やはり戸惑いを覚えます。
供養の場を単なる商品として扱う風潮が広がってしまえば、祈りやつながりといったお墓の本質が失われかねません。
お墓は形ではなく、亡き人を悼み、祈りを通して、いわば先祖と子孫がお互いに幸せを交換するための場です。形が変わっても、そこに祈りやつながりといったお墓の本質が宿ること——それが何より大切だと、私は思います。

AI生成によるイメージ画像(実際の墓地とは関係ありません)
簡素化の流れの中で
今は葬儀でもお墓でも簡素なものを選び、費用を抑える傾向が強くなっています。費用の負担を心配されるあまり、「最近はこういうのが流行りだから、これでいいんだ」と思い込んでしまう方も少なくないように感じます。
もちろん私は、無駄にお金をかけることを勧めたいわけではありません。けれども、人が一人亡くなるということは、それだけ長い年月の歩みと、積み重ねられた物語があるということです。なるべく良くしてあげることで、後からの後悔を減らせるのではないかと思います。
人の心の奥深いところ
葬送に関わることが全て変わりつつあるとは言っても、人の心の奥深い部分はそう簡単に変わるものではないと私は思います。特に冠婚葬祭に関わることですから、普段のライフスタイルとは別物で、せめてこういう時くらいは丁寧にしてあげたいと考える人がいても、少しもおかしくはないと私は思います。
ところが今は、葬儀やお墓に関するニュースのコメント欄などでは、そうした考え方がすぐに「時代遅れ」、「無用のもの」と片付けられてしまうことが多いように感じます。けれども、自分の家族や親しい友人が亡くなったときに、本当にそんなに簡単にドライに割り切れるものでしょうか。
一般論と自分自身の身の回りの出来事とは、やはり違うと思うのです。
多様な選択を尊重しつつ
私は、簡素なものを選ぶこと自体が悪いとは思いません。海洋散骨や樹木葬なども、それがふさわしい人にはきちんと意味のある選択だと思います。大切なのは、それぞれの事情に合わせて、自分の意志で納得して選ぶことです。どのような選択であっても、それぞれの方が納得して選んだものであれば、それを尊重したいと思います。
多様な供養方法がある今だからこそ、それぞれの選択が尊重されるべきだと思います。そのうえで、「お宅はそうじゃないだろう」という場面では、しっかり説明し、納得して選んでいただけるよう、一石屋として意見を述べていきたいと思います。
未来への責任として
私はこの先数十年経ったとき、未来の人たちから「なぜあの時代に日本人のお墓はこんなに本質を見失ってしまったのだろう」と嘆かれるようなことがあってはならないと思っています。たとえ形は変わっても、本質は変えない。そのための本質とは何かを、今の私たちがしっかり見極める必要があると考えています。
お墓は、亡き人を悼み、過去と未来をつなぐ存在です。そこに刻まれるのは流行ではなく、人の思い、家族の記憶です。どんなに形が変わっても、この本質が損なわれてしまっては意味がありません。
だからこそ、流行に流されず、自分たちが次の世代に何を残すのかを考え続ける必要があると思います。
この記事が、皆さんにとってお墓や供養について考えるきっかけになれば嬉しく思います。
では。
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております
 (有)吉澤石材店 吉澤光宏
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム