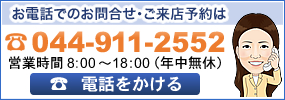石屋が旅先で出会った古い石塔に学ぶこと――城崎と国東
2025年8月13日(水)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
お盆のお休みに入りました。『学ぶ』だなんてタイトルを掲げてしまい引っ込みがつかなくなっていますが…汗。今日は今年の半期で訪れた石造物たちの中で個人的にも印象に残ったものを振り返ってみます。
まず3月に訪れた兵庫県の豊岡市、城崎温泉にある温泉寺の宝篋印塔。

城崎・温泉寺宝篋印塔
建てられたのは鎌倉時代の後期から南北朝の初期とされています。笠の四隅にある隅飾り(すみかざり)が直立より少しだけ外傾しているのはこの頃のに建てられた宝篋印塔の特徴です。相輪と呼ぶ先端の細長い部分は宝珠・請花の下で折れていましたが、後補ではなく完存。けっこうこの部分だけダメになって後に補っている石塔も多いので、オリジナルで残っているのはすごいものだと思います。花崗岩製で落ち着いた感じのする美しい石塔ですね。
重要文化財指定されています。
続いて4月末に訪れた大分県、国宝指定の摩崖仏群がある臼杵市の中尾五輪塔。

臼杵・中尾五輪塔(嘉応塔・承安塔)
在銘の五輪塔としてはわが国で二番目に古く、平安時代後期の嘉応二年に造られた一石五輪塔(一つの石で作られたということ)。嘉応二年って西暦で言うと1170年!なので、今年で建立後855年を経過した石造物です。後の鎌倉時代に造られる五輪塔と異なる造形で、ずんぐりとしたシルエットでどこか愛らしさを感じさせてくれました。
凝灰岩製で一部を欠損していますが、彫られた梵字も銘もよく残ってきたものです。保護のための上屋がかかっているのでこの先の劣化はだいぶ軽減されそうですね。重文指定されています。
そして同じく大分の国東市 岩戸寺の国東塔。

国東・岩戸寺宝塔
国東塔とは大分の国東半島あたりに残る独特の形をした宝塔で、大きな石の上にそびえ立つ姿は圧巻です。全体的なシルエットも独特ですが、蓮華も格狭間もしっかりとつくられているし、相輪の上にある宝珠が火焔つきというのも国東塔ならではということ。関東では見かけない石造物なので強く印象に残りました。
この塔も在銘、鎌倉時代中期の弘安六年(1283年)の建立は有名な元寇・弘安の役の二年後!。出来てから742年経過ということですね。重文指定の安山岩製の石塔です。
最後は同じく国東市 照恩寺の国東塔。大分を巡る石造物のたびの最後に出会った宝塔です。

国東・照恩寺宝塔
どことなく女性的な雰囲気、岩戸寺や他に拝した国東塔と比べて繊細な印象で、美しさが際立った塔に感じました。蓮華座がなく返り花だけなのでよりスッキリとした感じになるのかもしれませんね。明治期の廃仏毀釈の動きにやられ、近くの神社の池に投げ込んであったという話をお寺の方から伺いました。叩き割られたりしなかったのはこの塔のためにもかえって良かったのかもしれないなと思いました。
建立は鎌倉時代後期の正和五年(1316年)と岩戸寺宝塔より33年後。同じく重文指定されています。
ここ数年、業界団体の催しで各地におもむくとき、それにあわせてその地の石造物を見て歩くのがひそかな楽しみになっています。学術的なことなどわかりませんし、それほど突っ込んで追求しているわけではありません。ですがやっぱり美しい石塔を見ることで目が養われるはずで。
実際に石屋の仕事としてこうした石塔を建立する機会は決して多くはないですが、少なくとも何かの時にきっと役立つであろうと思っています。
石塔の様式は時代が下ってくると装飾が華美になり、本筋の部分がいつしかなおざりになってしまったように感じることがあります。もちろん近世の石工さんのお仕事を批評する立場にはなく、またそうした気持ちなどまるでありません。
そうしたことは別として、古の石工さんたちの手による造形美をしっかりと目に焼き付けておく。そうしたことも今を生きる石屋として、とても大事なことなのかなと私は思っています。
まだ会ったことがない美しい石造物に、これからもまた会いに行く機会ができるとありがたいですね。では。
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております
 (有)吉澤石材店 吉澤光宏
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム