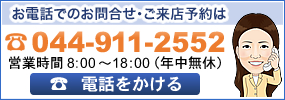土俵とお墓──文化の連続性について考えてみた
2025年11月24日(月)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
土曜のニュースで、高市総理が大相撲の千秋楽
で、優勝力士に授与する総理大臣杯の場面では
土俵には上がらない方針を固めた、という報道
を目にしました。
女性首相として初の機会に、
土俵に上がるのかどうか――。
さまざまな立場から意見が出てくるのは
当然でしょうね。
相撲は「国技」と言われますが、
実際には法律で定められた国技ではありません。
ただそれでも、神事として続いてきた歴史や、
宮廷儀礼としての長い積み重ね、さらには
地域に親しまれてきた長い時間があり、
今の大相撲につながっています。

儀礼の場としての土俵。
その土俵に女性が上がるかどうかという議論は、
単なる是非の問題ではなく、文化全体を
どう見つめるかという問いでもあります。
近年は、伝統文化に対して「差別だ」
「時代遅れだ」といった、刺激的な言葉が
先に立ってしまうことがあります。
もちろん、そうした意見があるのも理解します。
ただ、それだけで文化の本質を判断するのは
少しもったいないのかなあと、私は感じます。
この構図は、私たち石屋が向き合う 『お墓』
の文化にもよく似ていると思います。
最近、「お墓は明治以降の制度だ」「江戸時代の
庶民は墓など持っていなかった」といった主張を
耳にします。
確かに、京都の鳥辺野のように風葬が行われた
地域や、村外れに捨て場があった時代
もあるでしょう。
しかし、それが日本全体の姿だったわけではありません。
中世には五輪塔や板碑といった石塔が用いられる
ようになり、室町から戦国の頃には墓制が広がり
を見せ、江戸期になると庶民層でもお墓を持つ
ことが、次第に一般化したようです。

中世からのお墓文化の連続性を物語る石塔。
こうした千年以上続く深い連続性があってこそ、
今の“お墓の文化”につながっています。
ところが昨今は、数字や強い言葉が注目を
集めやすいせいもあってか、
「墓じまいの増加=お墓はもう不要だ」という
短絡的な図式が、どうしても前面に出やすい
ように感じます。
さらには「管理不要」「費用削減」「自然に還る」
といった、耳触りの良い言葉だけが並ぶ広告も
目につきます。
それ自体が悪いわけではありません。
ただ、そうした言葉の便利さだけに目を向けて、
お墓が本来持っていた意味、「先祖を弔い、
家族の祈りを重ねる場としての役割」を
考える機会が失われていくとしたら、それは少し心配です。
こうした耳触りの良い言葉は、反応を得やすい
からこそ、広まりやすい面があります。
しかし、それだけでは文化の本質や、
長い歴史の流れは見えてきません。
「お墓はもう不要だ」という大きな声ばかりが
取り上げられて、実際には日本人の多くの方が
静かに大切にしている――そんな現実が
見えにくくなりつつあることに、
私は危機感を覚えています。
お墓を本当に大切に思っている人たちは、
わざわざ声を上げることはありません。
伝統とは、本来“守れ”と叫ぶものではなく、
暮らしの中で静かに続けていくものだからです。
しかし、静かな多数派は目立ちません。
その一方で、刺激的な意見や数字ばかりが大きく
取り上げられる。
私は、その構図そのものが文化を歪めて
しまわないか、と不安を覚えます。
相撲の土俵の話題から、伝統が“声の大きさ”で
評価されてしまう、現代の空気を感じました。
お墓の文化もまた、その風に巻き込まれつつあります。
お墓は、国家の儀礼ではなく、日本人の祈りの
文化です。ゆえに派手さはありませんが、
だからこそ、静かに続いてきた意味があります。

家族でのお墓参りの際、家の歴史や思い出を
ほんの一言だけ伝えるだけでも、
文化は静かに、次の世代へつながっていくはずです。
数字や表面的な意見に流される前に、
お墓がたどってきた長い歴史と、
今も変わらず続いている静かな思いを、意識してみてください。
そうした時間が少しでも増えると、石屋として
これほどうれしいことはありません。
では。
参考:
高市早苗首相は土俵に上がらず、協会に連絡 内閣総理大臣杯は首相補佐官が授与 九州場所千秋楽(11/22 Yahoo!ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/5144a0d10b0cb01d117579644c06d4fb1ce18863
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
 現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム