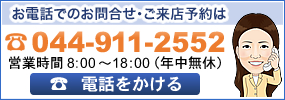墓じまい、その「数字のマジック」と現場のリアル
2025年11月19日(水)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
最近、「墓じまいが10年で2倍に増えた」「愛知の寺に2万5000基の“不要墓石”」といった、
インパクトのあるニュース記事を見かけることが増えてきました。
そんな見出しを見ると、不安になったりしませんか?
確かに、うちの石屋も以前より「墓じまい」の相談は増えていますし
時代の流れとしてその傾向にあることは否定できません。
ただ、報道される数字やそのトーンを見ていると、
どうしてもひとつの違和感がぬぐえないのです。
数字だけで判断する前に、石屋として現場に立つ者が感じていることを
少しお話しさせてください。
数字は「増えた」が、もともとの数は?
もともと、昔は墓じまいをするようなケースは非常に稀でした。
一度お墓を建てたら、そこは“家の場所”として
子々孫々つないでいくのが当然だったからです。
ところが近年は、少子化や非婚化などの影響で
「家を継ぐ人がいない」という状況が増えています。
そうなれば、お墓を守ることが難しくなり、
やむを得ず墓じまいを選ばれる方も出てきます。
しかし、だからといって「墓じまいが10年で2倍!」という数字を
そのまま大ごとのように受け取ってしまうのは、
少し危うさもあるのではないかと思うのです。
なぜなら、もともと“ゼロに近い件数”だったものが増えれば、
それは相対的には「倍」や「10倍」といった数字になります。
でも実数としてはどうでしょうか?
それはまったく別の問題ではないでしょうか。
公営霊園の「再利用率」が物語ること
少し具体的な話をしましょう。
私の地元・川崎市の市営霊園である「緑ヶ丘霊園」は、
およそ2万5000区画を超える墓所数を抱えています。
ここでは、墓じまいや使用者変更などで空いた墓所を、
翌年度以降に「再募集」という形で公表・告知しています。
この“再募集”に出される墓所数は、近年は毎年100区画程度です。
令和7年(2025年)の募集も100区画ほどでした。
石屋としての実感で言えば、墓じまいで解体される
お墓の数は、以前より確かに増えています。
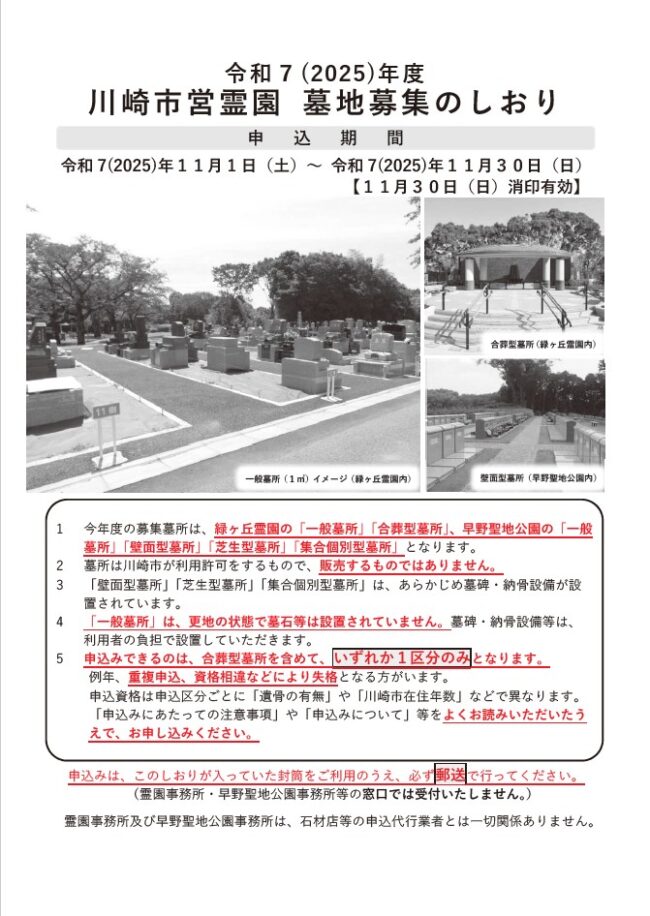
もちろん、墓じまいなどで空いた区画をすぐに再募集に回せるとは限らず、
区画の配置や周囲との兼ね合い、行政側の運用方針なども影響しますが、
それにしても2万5000区画中の100区画。
これは割合で言えば、1%にも満たない非常に小さな数字です。
つまり、「墓じまいで空きがどんどん増えている!」
という印象があったとしても、現実には公営墓地において
すぐさま“空きだらけになる”ようなことは起きていないのです。
なお、報道などで取り上げられる各種データの中には、
特定のポータルサイトを通じた一部の利用者に基づくものもあります。
たとえば鎌倉新書の調査は「いいお墓」経由の建墓者データであり、
建墓全体の傾向を、そのまま反映したものとは言えない
と私は思います。
一気に「合わない」と切り捨てるのは早計では?
最近では「お墓はもう生活スタイルに合わない」
そんな声も多く聞かれます。
気持ちはわかりますし、価値観の変化は避けられない
ことだとも思っています。
ただ、いきなり「もう、お墓が時代に“合わないもの”になった」
と決めつけるのは、あまりに急で、
やや暴論ではないかと感じるのです。
私は心配しています。
亡くなった方を敬い、たとえ姿は見えなくても、手を合わせることで
身近に感じることができる。そんなお墓の力や役割を、深く考えることなく
「もういらない」「不便だからやめる」と閉じてしまう。
そうした事例がこれから増えてしまうのではないかと。
石屋としての葛藤
もちろん、石屋という立場で言えば、墓じまいも大切な仕事の一つです。
建墓が減っていく中で、墓じまいを数多く依頼されることは、
経営的にはありがたいことでもあります。
でも、私はそれだけでは割り切れません。
もし「まだ解体しなくてもよいお墓」までが、
何となくの風潮や雰囲気で壊されてしまうようになったら……。
それはつまり、日本人のお墓という文化が、形だけが残り、中身が失われていく
“骨抜き”のような状態になってしまうのではないか。
そんな危機感も覚えています。
墓じまいそのものを、否定するつもりはない
ただ、数字のインパクトに流されたり、社会の空気に飲まれたりせず、
「私たちは何を残すのか」「何を手放すのか」を、
立ち止まって考える機会があってもいい。
そう願うのは、石を刻み、積み、お墓を通じて
家族の記憶を守ってきた者としての、ささやかな思いです。
不安ではなく、冷静な判断を
墓じまいが増えていると聞いて、不安になる必要はありません。
もし、あなたに子どもがいて、小さくても孫がいるなら。
今お墓を建てたとして、その孫が年を重ねるまで、
たとえば50年近い年月があったとします。
そして、仮にお墓を建てるのに300万円かかったとします。
決して安い買い物ではありません。
でも、50年で割ってみてください。
年間6万円。月にすれば5,000円です。
200万円なら年4万円、月3,300円ほど。
150万円なら年3万円、月2,500円です。
その50年の間、家族が心豊かな気持ちで、
先祖に手を合わせることができる。
お盆に、お彼岸に、命日に。
「ここに来れば会える」という安心がある。

これは、決して余計な出費とは言えないのではないでしょうか。
もちろん、最後にお墓を閉じる時には、
その費用が発生するかもしれません。
ただ、それはまた別の話でしょう。
50年先のことを心配して、今必要なものを
諦める必要はない。
「今、必要な人がいる」「今、続けられる」と思えるなら、
その選択は間違っていないと、私は思います。
数字のインパクトに惑わされず、自分たちの未来を見据えて決める。
そうして建てられたお墓は、何十年先も家族の支えになるはずです。
では。
▼あわせて読みたい続編:
解体≠墓じまい。「見た目のマジック」とお墓の再出発
参考:
まさに“墓の墓場” 愛知の寺に2万5000基「40年前からは想像がつかない量に」
増える墓じまい、一方で処分には抵抗感も “お墓”の必要性とは(11/15 Yahoo!ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/5144a0d10b0cb01d117579644c06d4fb1ce18863

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております
 (有)吉澤石材店 吉澤光宏
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム