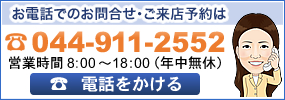能登支援は、未来への備え。一人の負担を、百人で分け合うために
2025年11月15日(土)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
昨日まで、能登で行われている災害支援に参加してきました。
今回は川崎石材商工業組合の若手二人を連れての参加です。
うち一人は、今回が初めての災害現場。
実際に倒れたお墓を目にして、きっといろいろと感じるものがあったと思います。
現場では、写真では伝わりきらない”重さ”があります。
そこにあったのは石の被害というより、亡くなった方を守ってきた家族の思いが
断ち切られた光景でした。

七尾市寺院墓地:地震の被害に遭った墓所(11/14)
私たちの役割は”縁の下”
能登の現場で私たちが行うのは、お墓を直す作業そのものではありません。
修復に入るための前段階、つまり石の整理と安全確保の仕事です。
倒壊した石を番号管理し、危険なものを安定させ、二次災害の危険性を低くさせる。
その作業をすることで、地元の石材店さんが本格的な修復に入る助けをすることです。
実際にお墓をもとの姿へ戻すのは、地域の石屋さんです。
日頃からご家族と向き合い、地域の習わしを知り、
その地に根づいて施工してきた職人でなければ務まらない仕事です。
私たち外部からの支援は、その前段階を整える”縁の下”の役割であり
決して営利目的ではありません。

輪島市寺院墓地:傷んだ本堂脇の階段を上がった斜面に、墓地が点在(11/13)

輪島市寺院墓地:斜面から滑り落ちた石、倒れた石をもとの墓所に戻し、整理して仮置き(11/13)
前回の支援活動で時間を共にした仲間もいます。初めて出会う方もいます。
作業中には道具の使い方や施工の考え方など、普段はなかなか聞く機会のない話が
自然と飛び交います。
夕食を共にしながら、それぞれの地域で抱える課題、災害を経験して見えてきたこと、
思いなどを語り合う時間もありました。
若手にとっては、現場の体験に加えて、こうした”横のつながり”から
得る学びも大きかったはずです。
被災地のため、未来の自分たちのため
正直に言えば、私たちが一度現場に入ったからといって
復旧が劇的に進むわけではありません。
能登の被害の広さ・大きさを前にすると、どれだけの時間と労力が必要になるのか
想像もつかないほどです。
完全な復興に向け、積み重ねられるべき作業の多さを思えば、
私たちの一度の活動は、その中のごくごく一部にすぎません。
まさに、微々たるものだと感じます。
それでも、私にはこの支援が大きな意味を持つと感じています。
たとえて言うなら、1人で100回必要な手間があるとすれば、100人で分け合えば一度で済む。
誰か一人に過重な負担がかかり続けるのではなく、”みんなで少しずつ肩を貸す”ことで
それが大きな推進力となる。現場ではまさにそれを実感します。
そしてもう一つ。
次の支援があるとして、私が必ず参加できるとは限りません。
参加者の誰もが、現場の状況、体調、仕事の進み具合。
どんな理由であれ、行けない時はあります。
しかし、それで支援が止まることはありません。
別の日には別の地域の仲間が現場に立ち、必要な作業を進めてくれる。
まるで襷をつないでいくように、誰かがバトンを握り、渡し続けていける
石材業界であってほしいと願います。
これは能登だけの話ではありません。
日本のどこで災害が起きるかは誰にも分からない。
今日支援している地域の姿は、明日の自分の地域の姿かもしれません。
だからこそ、被災地での活動はそのまま「自分たちの未来のため」の
作業にもなるのだと思います。
支援の現場で得た経験は、必ず自分の地域に持ち帰ることができる。
もし自分の地元で災害が起きたとき、どこを見て、何から手をつけ、
どう人と連携するのか。
能登での経験は、そのとき立ち戻る一つの灯になるはずです。
支援とは、被災地を助けると同時に、未来の自分たちを助ける営みでもある。
そう考えると、今回若手二人と共有できた時間は、
作業そのもの以上に価値のあるものだったように思います。
では。
【関連記事】
今回の能登支援の一連の流れは、以下の記事でも綴っています。
・2025年11月11日公開「明日、奥能登へ――川崎の石屋が若手に伝えたい経験とは」
・2025年11月12日公開「輪島まで24km――去年と同じ道、変わったこと、変わらないこと」
・2025年11月17日公開「お墓と向き合う者として。 一介の町石屋が能登支援で感じたこと」

※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております
 (有)吉澤石材店 吉澤光宏
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム