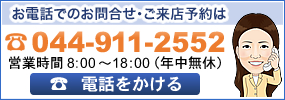散骨とお墓。そのあいだにある人の思い
2025年10月31日(金)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
少し前、10/25のYahoo!ニュースで『石原家の兄弟』というエッセイ集のことが記事になっていました。
ベストセラーとなっているようですが、長男の伸晃さんがあとがきで「初版の一冊は両親のお墓に持って行こうと思う」と書かれているそうです。
これを読んで、ふとおもいました。
父である石原慎太郎さんは「骨は必ず海に散らせ」という遺言を残していたそうです。
そして、実際に葉山町沖で散骨されました。
ただ、遺骨の一部はきちんとお墓にも納められているそうです。

海に還った父に、息子は「お墓」で報告しようとしている。矛盾しているように見えるかもしれません。
でも、これはむしろ供養の本質なんじゃないかと思うんです。
散骨を選ぶ方は増えているそうです。「自然に還りたい」「家族に負担をかけたくない」。そんな思いをネットで目にします。
遺族も、故人の願いを叶えてあげられたという満足感は持つでしょう。
でも時が経つにつれて気づくんですね。
ふと手を合わせたくなったとき、報告したいことがあったとき、やっぱり確かに向き合える場所が欲しいと思うんじゃないでしょうか。
遺された人には、語りかける場所が必要なんです。
人はどこからか突然生まれてきたわけじゃありません。親がいて、自分がいる。そして子供がいる。
もちろん子供がいない人もいます。それでも私たちは誰かとのつながりの中で生きています。
だから思うんです。自分の死後について考えるとき「自分がどうしたいか」だけで決めてしまっていいのかなと。
残される人の気持ちはどうか。次の世代がどう感じるか。そこまで想像してみる必要があるんじゃないでしょうか。
そして、いわゆる墓じまいも同じですね。
「維持が大変だから」「子供に負担をかけたくないから」と先祖代々の墓を処分する。
その判断は今の自分には合理的に見えるかもしれません。
でもその先の世代が「先祖とつながる場所が欲しかった」と思うかもしれない。
供養というのは、故人だけのものじゃないんです。遺された者たちのためのものでもあります。
自分の思いも大切。でも家族の思いも大切。
そのどちらも考えながら、ゆっくり答えを見つけていけばいいんじゃないでしょうか。
それが、世代を超えたつながりの中で生きる
ということなのかもしれません。
では。
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
 現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
現地確認。お見積り・ご提案はすべて無料です。
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム