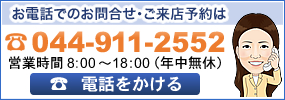雨の日のお墓工事が危険な本当の理由【川崎の石屋が解説】
2025年9月6日(土)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
昨日は台風が近づいたため、とても久しぶりにまとまった雨になりましたね。現場作業に出られないこんな日には、なぜ私たちが雨の日にはお墓の据付工事を絶対にしないのか、その理由を少し書いてみますね。決して濡れるのが嫌だから、という単純な話ではありませんよ。もちろん好きではありませんが(笑)、大切なのは安全と工事の品質を守るためなんです。
読みやすいように、いくつか項目ごとにまとめます。
①安全面の問題
石の表面は磨くと摩擦係数が低くなり、濡れると非常に滑りやすくなります。そのため最近ではお墓の階段や敷石の踏面は本磨きではなく、サンドブラストや叩き仕上げで荒らすことが多くなっています。でも大部分は磨き仕上げなので、石を持つのもそれなりに滑る危険性をはらみます。
また、石を吊るクランプという道具も、石の表面に水の膜ができることで滑りやすくなります。重い石が吊り上げ途中に落下すれば大事故へとにつながる可能性も…。いくら拭いても完全に乾かせるわけではありませんから、雨の日は据付作業を避けるんです。

石を吊るための「クランプ」。雨で石が濡れていると摩擦力が弱まり、滑りやすくなる
②工事の品質面の問題
もう一つの理由は工事の品質を確保するためです。現代のお墓施工では石同士の接着に専用の接着剤を使いますが、これは水濡れは絶対に厳禁です。どんなに良い接着剤でも濡れた面には密着せず、硬化してもすぐ剥がれてしまいます。
実際にとある被災地で倒れたお墓を見たとき、接着剤の跡がツルツルのまま残っていたり、あるいは倒れた石のほうに接着剤が持っていかれて、合わさった面はまったく接着剤が残っていない。そうした事例がありました。通常なら剥離面は両側に残りザラザラになるはずですが、そうなっていない。おそらく施工時に石が湿っていた(あるいは面に汚れがついていた可能性も)のだと思います。
ここで写真2枚を上げてみます。

接着剤が正しく効いていたケース。無理に剥がせば接着剤が石の両側に残り、引きちぎられた表面はザラザラになる

接着剤が効いていなかったケース。片側の石に持っていかれて石の面に接着剤が残っていない。
こうした写真からも、接着剤の施工不良がいかに危ういかということが理解できるのではないでしょうか。
以前に、石の表面をバーナーであぶって乾かしてから施工している施工者を目にしたことがあります。しかしこれも避けたい方法です。なぜなら石は見た目には平らでも、軽石やスポンジのように微細な穴が無数にあり、そこに水を吸い込んでいるからです。表面をいくら乾かしても内部の水分がじわじわと上がってくるため、やはり施工不良を招いてしまいます。
③昔のモルタル施工との違い
昔はモルタルで石を据え付ける方法が主流でした。この場合は今ほど雨の影響を受けず、そこまで神経質にならずに施工をしていました。ブルーシートで覆い雨をしのげれば、むしろ多少湿っていた方がモルタルのドライアウトを防ぎ、状況によっては好ましい場合もあったくらいです。
とはいえ大雨では到底無理、それに現場の周辺だって長靴についた土などでかなり汚してしまうことにもなりますし。納期が近くて仕方のない場合に限っての話ですよね。
④現場での判断と姿勢
いずれにしても、今の施工では雨の日の据付作業は絶対に避けるべきです。もちろん工事中、急な降雨に見舞われることもあります。その場合は小雨なら養生して石を濡らさないよう注意をし、大雨で濡れてしまえば拭き取って自然に乾くまで待ちます。そして、場合によってはその日の作業を打ち切ることもあります。
それは仕事を託してくださった施主様のためです。ここだけは絶対に譲ってはならない部分です。
もちろん、納期が迫っている時は気が気ではありません。それでも無理な施工は結局、お客さんの不利益に繋がります。状況を説明し、ご理解いただいた上で一番よい状態で仕上げること。それが長く安心していただけるお墓につながると信じています。
では。
ここで述べている「雨の日に避けるべき作業」とは、主に石を据え付ける作業や接着剤を使用する作業のことです。お墓の清掃や雑草取り、資材の運搬など、雨天でも大きな支障のない作業もありますので誤解なさらないでください。
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております
 (有)吉澤石材店 吉澤光宏
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム