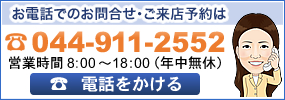見直したい身近で産する石の価値と可能性 札幌軟石を訪ねてみて
2025年7月26日(土)
こんにちは。川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
毎日暑い日が続きますね。今日は午前中地元町内会の盆踊りのやぐら組みに行ってきました。はい、もうあっという間に汗だくでしたね。数日前には北国の北海道で40℃近い気温を記録したとか!異常気象ではなく既にこれが日本の夏のデフォルトなのかもしれません。
そういえば先月中旬には石材業界の団体の年次総会で北海道に行ってまいりました。ちょうど思い出したのでその時のことから一つ拾って書いてみますね。
総会といってもただ会議だけじゃなく、いくつかのオプショナルツアー的なものも用意されていて私は『札幌軟石』と呼ばれる凝灰岩の採掘地を見学してきました。その時も日中はもう結構な気温で、爽やかな気候のはずだったんじゃないの?と思ったことを覚えています。

とにかくカンカン照りで日傘をさしながらの見学。御影石の丁場とは趣きが異なります。グレー系の石肌、チェーンソーで挽く採り方は何となく関東で流通する『白河石』や『芦野石』という石材にも似ていますね。

職人さんの足元にある溝は手にした刃で大地(石)を挽いた跡ですよ。硬い石をこんなのこぎりで挽くのってなんだかすごいと思いませんか?それと溜まった切粉の量も半端じゃない。採掘場全体にこの切粉が大量に溜まり、風が吹けば石粉の粉塵が舞い上がります。靴も当然真っ白ですね!
粉塵と闘いながら石を採る職人さんたちには頭が下がります。どんな石も大変な作業のおかげで世に出ているのを再認識しました。
そんな札幌軟石、北海度では大変多く使用され愛されてきた石材です。街を歩けばこの石がたくさん使われています。昨冬に訪れた時に撮っておいた写真ですが…。


札幌市資料館や北大構内にある札幌農学校時代の建物。おそらくは凝灰岩の性質上、耐火性に富みある程度の調湿効果も期待できはずであり、かつ札幌近郊が採掘地という利便性。それゆえに明治期の建築物の構造材としてこの石が選ばれてきたのでしょうね。
たまたま覗いた北海道大学博物館にも軟石の展示がしてありました。



ひとつの石でも仕上げによってこれほどまでにテクスチャ(質感・手触り)が変わります。昨日上げたブログで犬島石の叩き仕上げに触れましたが、あちらは花崗岩。札幌軟石は凝灰岩という種類の違いこそありますが、石の素材としての面白さや可能性を感じさせる気がします。
実はこの札幌軟石、現在では採掘業者さんは先ほどの採掘場をもつ一社だけになってしまったと伺いました。コンクリート製品の普及や建物のつくり方の変化などの影響で需要が少なくなってしまった影響なのでしょう。
また、関東でも以前では大谷石や白河石・芦野石がお墓の外柵にも使われてきたように、きっと北海道でも札幌軟石がお墓の外柵材としても使われていた時代があっただろうと思います。ただ最近では流通経路の発達でいろいろな地域から御影石(花崗岩や閃緑岩など)が入るので札幌軟石がお墓に使われる事例はなくなっているという話も聞きました。
時代の変化ということなのでしょうが、どこか寂しい思いがします。
それでも今回宿泊したホテルのエレベーターホールの内壁には、札幌軟石がしっかり使われていました。石屋の端くれとして地元の石が地元で使われているさまを見るのは本当にうれしい!
御影石よりも温かみを感じさせる素材、しかも人工物ではない本物が持つ味わいはどこか人をほっとさせてくれる力があります。同じく凝灰岩に分類される大谷石なども、素朴な柔らかい色調で店舗の内装材によく使われているのを目にするようにもなっています。柔らかい石でも雨のかからない屋内なら劣化も心配ありませんよね。

昨冬の訪問時、冬靴購入で立ち寄ったデパートの一角では札幌軟石についてのパネル展示も行われていました。

身近で産する魅力ある素材であるところの石。それぞれの地域で使われてきたそんな石たちがこの日本にはまだまだあります。
長く愛されてきた地元の石がさらに見直され建築材として、そしてお墓の材料としてもどんどん採用される機会を増やしていってほしいと願わずにいられません。
町石屋の私としても、本当に微力ではありますが石のことを発信していきたいと改めて思いました。
また何か書いてみます。
![]()
※最後までご覧をいただきまして、ありがとうございます。
お墓以外にも石鳥居や記念碑のお仕事も承っております
 (有)吉澤石材店 吉澤光宏
(有)吉澤石材店 吉澤光宏
ご相談・お問合せは、お気軽にどうぞ。
電話 044-911-2552 (携帯転送なので外出先でもつながります)
メール お問い合わせフォーム